キャリアプラン
Case01
一から優しく教えてくれる
先輩に支えられて
資格を不安なく取得することができました

私は9ヶ月ほど、派遣社員として前原興業株式会社で働いておりました。そのため、会社の様子がよく分かった上で就職先として選びました。
上司や職人さん達が優しく教えてくださるので、成長しやすい職場だな。と一番最初に感じました。
この業界は資格が沢山あるのですが、どんな資格が役に立つのかを先輩方が丁寧に教えてくださいました。職長・安全衛生責任者教育を最初に取得しています。会社が必要書類の準備や申込までやってくれる上に、交通費を含めた資格取得にかかる費用も全て会社が負担してくれたので、全く不安なく取得できました。知識が身につくので『一歩成長したな』と実感が湧いた瞬間です。
いま任されている主な仕事は、工事の進捗状況の確認や品質管理、安全管理などです。品質管理は製品の出来に関わる重要な作業なので、丁寧にやるように心掛けています。安全管理は自分の関わっている作業員の皆さんにその日の作業の注意点や立ち入り禁止箇所を周知します。イレギュラーな仕事に自分で工程を考えて、段取りがスムーズに対応できたときは、仕事に対して自信がもてる瞬間です。
休日もしっかりいただけるので、仕事を忘れて趣味に没頭できています。平日も趣味の予定があるときは、残業をしないように仕事を調整することができる事が魅力ですね。
今後は、現場で知識を学びながら、将来を見据えて資格を取得して確実にステップアップして行きたいと考えています。前原興業にはその為の環境が整っています。

Case02
『3年目から現場を持ちたいです。』と立候補。
先輩方のサポートをいただきつつ
現場を任せられています。

建築関係で働いていた祖父が亡くなりました。その祖父の関わっていた建築に『私も関わりたい』と思い面接を受けたところ、その日に会社のユニフォームを渡されました。お陰様で断れずに入社しました(笑)
一番最初に『職長・安全衛生責任者教育』を取得した時はとても嬉しかったですね。『これから建築の仕事を頑張る』という気持ちが強くなりました。職長とは、建設現場などで労働者を指揮する、労働者の健康と安全を確保する重要で責任ある立場です。
また、資格取得の時は受験料を会社が負担してくれるので、安心して受験に集中できました。
現在、『3年目から現場を持ちたいです。』と立候補し、先輩方のサポートをいただきつつ、現場を任せられています。やること、気にすることが1年目と2年目より遥かに多くて毎日必死に働いてます。特に、材料を上手く注文することで、材料待ちで職人さんの作業を止めることがないように心がけています。
3年経って様々な物件の仕事に関わり、何もない土地に一から携わってた建物作りが完成したときは一番やり切った感があります。現場によっては週6日の勤務ですが、その分、給料はいい方だと思います。前原興業は実力主義なので、頑張った分だけ評価されます。
今後は皆さんに入社していただき、社員が増え、完全週休二日制になれば更に働きやすくなることでしょう。皆さんの入社を楽しみにしております。

Case03
自分自身のスキルアップはもとより
後輩のサポートをしつつ
育成ができるように頑張ります。
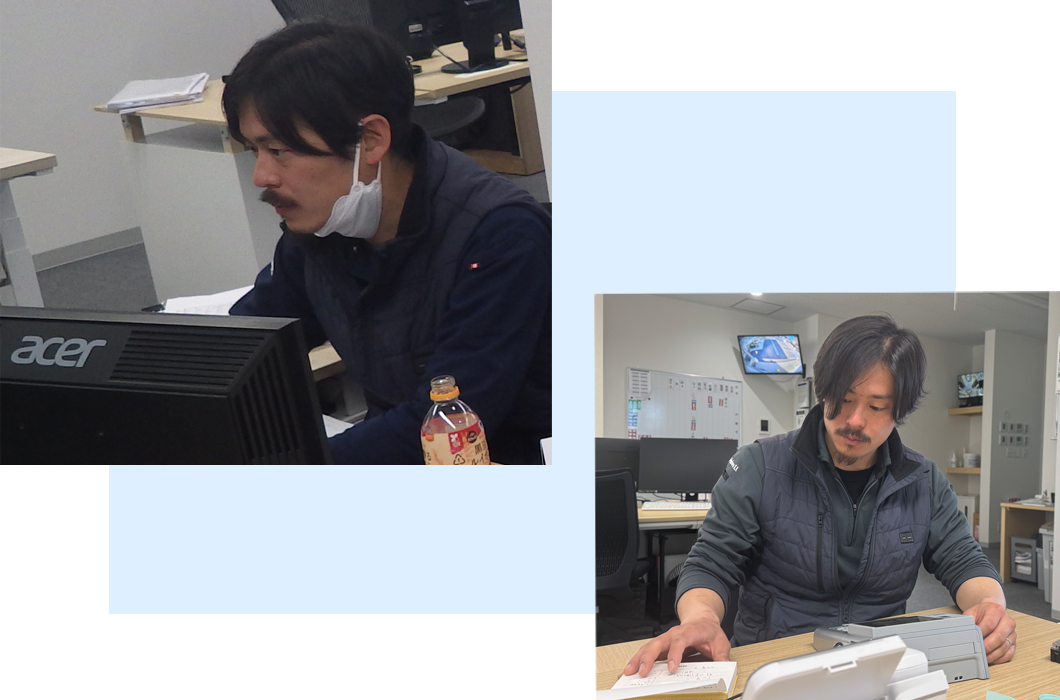
手に職をつけられるという事と、地域に根ざしている会社という事で前原興業株式会社を選びました。
手に職という事で、資格取得についていうと、施工管理に関する資格で1番最初に受験した工事の専任技術者になれる2級管工事施工管理技士を取得できたときが一番嬉しかったです。やはり、資格取得に力を入れているので、受験料や受講料を会社に負担してもらえるのは助かります。
また、資格とは少し違いますが、現場で特定の作業等を行う場合に必要になる技術研修や、現場でよく使用される機械等で事故が多いものに関する内容等に限定された特別教育があります。どちらも作業をする上での危険性等を学ぶことができるので、なるべく取得するようにしています。
仕事のひとつとして、施工図の作図と、その施工図を基に現場で職人さんが施工しているのを確認するという工程があります。配管ルートや勾配の検討などで悩むことも多いですが、実際に現場で配管されているのを見て、検討した通りだった場合や、うまくいかなかった場合など、自分の目で見て確認できる時が充実していると感じます。
建築の自社設計施工の分譲マンションの現場を担当しています。分譲マンションを担当するのが初めてだったのでわからないことだらけでしたが、設計や設備担当の方に細かく教えて頂いたことが今でも力になっています。現場でも所長や次席に助けて頂き、成長することができました。
通常、新築の共同住宅であれば入社3年目くらいで現場を任される事が多いのですが、私の場合は、改修を1年目からサポート付きで担当させていただきました。
今後は、自分自身のスキルアップはもとより、後輩のサポートをしつつ育成ができるように頑張ります。








